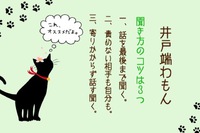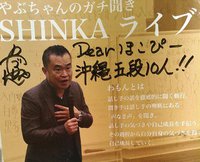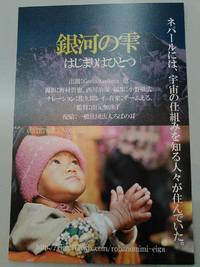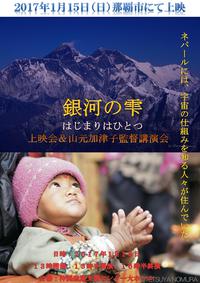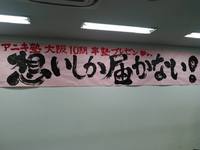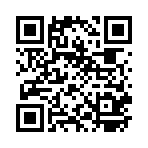› いのちにつながる › 心理的に苦しい人は読んで下さい。無理をしないで下さい
› いのちにつながる › 心理的に苦しい人は読んで下さい。無理をしないで下さい2011年03月17日
心理的に苦しい人は読んで下さい。無理をしないで下さい
「非常時に「心」に起きる変化とは」より転載です。
http://wol.nikkeibp.co.jp/article/trend/20110316/110388/
http://wol.nikkeibp.co.jp/article/trend/20110316/110388/?P=2
http://wol.nikkeibp.co.jp/article/trend/20110316/110388/?P=3
東日本巨大地震後、津波や相次ぐ余震、原発での未曾有の事故のニュースが飛び交っています。救援物資の手配や原発被害を食い止めるための措置、計画停電などの情報とともに、被災地の惨状を目の当たりにした人々の心の負担についても言及され始めました。避難所によってはメンタルヘルスのための簡易的な診療所を設けているところもあるようです。大きな事故・災害・犯罪などが起こって1ヵ月ほどの間に人々の心の中ではさまざまな反応が起きます。PTSD(心的外傷後ストレス障害)と呼ばれる症状が現われてくることもその1つです。
ショッキングな出来事に遭遇したとき、人の心はどのようになるのでしょうか。また、被災者ご本人、被災者をご家族に持つ方、被災者ではない方、それぞれが今できる心のケアにはどんなものがあるのでしょうか。
まずは、心の「防衛機制」について知ること
私たちの心は、日常的に感じるストレスにうまく適応するために常にバランスを取っています。その心に多大な負荷がかかったとき、一種の非常制御装置がはたらくのです。「これ以上負荷をかけると処理が追いつかなくて心が崩壊してしまいますよ」というアラーム。これが「防衛機制」の発動です。
心を守るために発動した防衛機制は様々なストレス反応として現れてきます。ストレス反応には、動悸や腹痛、頭痛、吐き気、めまい、発汗、食欲不振、不眠などの身体的なものと逃避、過度の依存、攻撃、感情鈍麻、無気力、記憶障害など心理的なものがあります。そのほか、日常的な行動面でもさまざまな変化が見られます。
心が崩壊してしまうのを未然に防ぐためで、多かれ少なかれ、誰もがそうなる可能性があります。これは、人間的に強い弱いの問題ではありません。ただし、実際に心が崩壊してしまうのではないかと感じる基準は人それぞれ。よって、同じ体験に対してすべての人に同じ反応が出るわけではなく反応の度合いも異なります。
「防衛機制」による症状には、例えば、下記のような症状があります。
・もの忘れがひどくなった
・考えがうまくまとまらない
・感情が動かず何も感じない
・眠れない、もしくは過剰な睡眠
・食欲がない、もしくは過剰な食欲
・真剣な場でも顔が笑ってしまう
・場にそぐわない冗談を言ってしまう
・取り組むべきこと以外に気がそれる
・批判的になる、攻撃性が出る
・無気力で何もする気が起きない
・不自然なポジティブ思考
・自信や自己肯定感の喪失
一見、逃げているように見えたり不謹慎な態度に見えたりしてしまうこんな症状。表からはわかりにくいのですが、心の中では懸命な復旧活動が行われている場合があります。
防衛機制としてのストレス反応は、いわば困難からの一時待避。そして、遭遇してしまった困難な現実に再適応するための大切な心の仕組みなのです。想像を絶する大災害に見舞われた被災地の方、家族や知人の安否確認に血眼になっている方、不眠不休で陣頭指揮をとっている政府や関連企業の方、そしてそれを間接的に映像などで目撃された方も例外ではありません。緊張を余儀なくされる今の状況では、それぞれの心の防波堤がフル稼働しているはずです。自分自身や周囲の方々がいつもと違う様子であったとしても、どうか互いに温かく見守っていただければと思います。
それぞれの立場でできること
被災地にいる方であれ、被災者を家族や友人に持つ方であれ、心理的に心に留めておいたほうがよいことがいくつかあります。
まずは、無理に元気ややる気を出そうとしなくてもいいし、不安になってもいい、人の助けを借りたっていい、というように、とにかく自分の気持ちや感情に「許可をおろすこと」が必要かと思います。とにかく、自分の気持ちを肯定し、受け入れることが大事なのです。逆に、自分がいっぱいいっぱいなら無理して励ましたり慰めようとしなくたっていいのです。また、それができない自分を責めるようなこともやめましょう。
次に大切なことは、周りの人とのコミュニケーション。不安な気持ち、絶望的な感情を吐露できればいいのですが、立場や状況によってはそうもいきません。皆が気を張っている今、本当の気持ちを吐き出すには実は相当時間がかかります。あいさつでもいい、そっと触れるだけでもいい。とにかく、人の温かさを感じることが気持ちの安らぎにつながります。
家族や友人が被災地にいる、または安否が確認できないなどの状況に置かれている人も少なくないでしょう。気をつけるべきことは自分自身の気持ちが不安定な状態で無理に誰かを救おうとしないこと。自身が安全を確保していることに罪悪感を抱く必要もありません。引き続き災害に備えながらも、可能な限りの日常生活を続けることが心のペースメーカーとなります。
不安に駆られるときは、自分の気持ちや心配事をできる限り言葉にしたりリストアップしたりすると落ち着きます。
自分自身を冷静に見つめる
怖れは次の怖れを喚起します。自分自身の「怖さ」という気持ちのフィルターがかかった情報は、不安や焦りばかりが先行して伝播してしまいます。無用なパニックを避けるためにも、まず自分自身の気持ちをスクリーニング(ふるい分け)してみてください。
たとえ、被災地から遠いところにいる方でも、映像などで十分にショックを受けている可能性があります。自分自身が疲れや無力感を感じていること、不安や怖れを感じていることを踏まえた上で冷静な言動を心がけて下さい。そして自分自身の安全と健康確保も忘れずに。
休むことや食べることに罪悪感を持つことはありません。あなたが健康でいることも立派な支援です。無計画で衝動的な援助欲求は状況の混乱を招くだけでなく、燃え尽きなどによる共倒れの危険性をともなうことがありますので注意が必要です。
専門家のケアも大切
すでに大震災に関する報道の合間に、「テレビを観ている人もPTSDになる可能性があります」などというコメントを目にして不安を感じた方もいらっしゃるかもしれません。
確かにPTSDは誰もがなる可能性はありますが、大きな災害や事故に遭った方すべてがなるわけではありません。以下に、医療現場で用いられている診断基準の概要を紹介します。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
PTSD(心的外傷後ストレス障害)
危うく死または重傷を負うような出来事を体験、または本人や他者の身体の保全に迫る危険を体験・目撃・直面した。加えて、本人が強い恐怖や戦慄、無力感を覚えた。子どもの場合は極度の興奮として現われる場合も。このような体験をし、以下の基本症状が1ヵ月以上にわたって見られる場合にPTSDと診断される。
【PTSDと診断するための基本的症状】
・心的外傷と関連した出来事の追体験(フラッシュバック、悪夢など)
・心的外傷と関連した出来事に関連するものへの回避傾向、記憶障害、孤立、感情鈍麻、意欲減退など
・睡眠障害、易怒傾向、過度の警戒心や驚愕反応など
(参考文献:DSM-IV 該当項目の要約)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
大震災の爪痕が残る地で緊張を強いられながら過ごした後、上記のような症状が1ヵ月以上続く場合は専門家の診断の上で適切なケアをすることが求められます。実際にPTSDかどうかの判断や薬の処方は医師でないとできませんので、思い当たることがあれば医療機関や専門機関でのケアをおすすめします。
本人には自覚症状がなくても近親者がいつもと違う変化に気付くことでPTSDの兆候を早期発見できる場合もあります。
まだまだ新たな地震が続いており、心休まる暇もない方がたくさんいらっしゃることと思います。非常時に適応しようとする自分の心の力を信頼しながら、大切な方々と声を掛け合ってこの難局を乗り切っていきましょう。
【参考文献】
『DSM-IV』アメリカ精神医学協会
『心的外傷の危機介入』金剛出版
『グリーフワーク』アスク・ヒューマンケア
三吉野 愛子=心理カウンセラー
http://wol.nikkeibp.co.jp/article/trend/20110316/110388/
http://wol.nikkeibp.co.jp/article/trend/20110316/110388/?P=2
http://wol.nikkeibp.co.jp/article/trend/20110316/110388/?P=3
東日本巨大地震後、津波や相次ぐ余震、原発での未曾有の事故のニュースが飛び交っています。救援物資の手配や原発被害を食い止めるための措置、計画停電などの情報とともに、被災地の惨状を目の当たりにした人々の心の負担についても言及され始めました。避難所によってはメンタルヘルスのための簡易的な診療所を設けているところもあるようです。大きな事故・災害・犯罪などが起こって1ヵ月ほどの間に人々の心の中ではさまざまな反応が起きます。PTSD(心的外傷後ストレス障害)と呼ばれる症状が現われてくることもその1つです。
ショッキングな出来事に遭遇したとき、人の心はどのようになるのでしょうか。また、被災者ご本人、被災者をご家族に持つ方、被災者ではない方、それぞれが今できる心のケアにはどんなものがあるのでしょうか。
まずは、心の「防衛機制」について知ること
私たちの心は、日常的に感じるストレスにうまく適応するために常にバランスを取っています。その心に多大な負荷がかかったとき、一種の非常制御装置がはたらくのです。「これ以上負荷をかけると処理が追いつかなくて心が崩壊してしまいますよ」というアラーム。これが「防衛機制」の発動です。
心を守るために発動した防衛機制は様々なストレス反応として現れてきます。ストレス反応には、動悸や腹痛、頭痛、吐き気、めまい、発汗、食欲不振、不眠などの身体的なものと逃避、過度の依存、攻撃、感情鈍麻、無気力、記憶障害など心理的なものがあります。そのほか、日常的な行動面でもさまざまな変化が見られます。
心が崩壊してしまうのを未然に防ぐためで、多かれ少なかれ、誰もがそうなる可能性があります。これは、人間的に強い弱いの問題ではありません。ただし、実際に心が崩壊してしまうのではないかと感じる基準は人それぞれ。よって、同じ体験に対してすべての人に同じ反応が出るわけではなく反応の度合いも異なります。
「防衛機制」による症状には、例えば、下記のような症状があります。
・もの忘れがひどくなった
・考えがうまくまとまらない
・感情が動かず何も感じない
・眠れない、もしくは過剰な睡眠
・食欲がない、もしくは過剰な食欲
・真剣な場でも顔が笑ってしまう
・場にそぐわない冗談を言ってしまう
・取り組むべきこと以外に気がそれる
・批判的になる、攻撃性が出る
・無気力で何もする気が起きない
・不自然なポジティブ思考
・自信や自己肯定感の喪失
一見、逃げているように見えたり不謹慎な態度に見えたりしてしまうこんな症状。表からはわかりにくいのですが、心の中では懸命な復旧活動が行われている場合があります。
防衛機制としてのストレス反応は、いわば困難からの一時待避。そして、遭遇してしまった困難な現実に再適応するための大切な心の仕組みなのです。想像を絶する大災害に見舞われた被災地の方、家族や知人の安否確認に血眼になっている方、不眠不休で陣頭指揮をとっている政府や関連企業の方、そしてそれを間接的に映像などで目撃された方も例外ではありません。緊張を余儀なくされる今の状況では、それぞれの心の防波堤がフル稼働しているはずです。自分自身や周囲の方々がいつもと違う様子であったとしても、どうか互いに温かく見守っていただければと思います。
それぞれの立場でできること
被災地にいる方であれ、被災者を家族や友人に持つ方であれ、心理的に心に留めておいたほうがよいことがいくつかあります。
まずは、無理に元気ややる気を出そうとしなくてもいいし、不安になってもいい、人の助けを借りたっていい、というように、とにかく自分の気持ちや感情に「許可をおろすこと」が必要かと思います。とにかく、自分の気持ちを肯定し、受け入れることが大事なのです。逆に、自分がいっぱいいっぱいなら無理して励ましたり慰めようとしなくたっていいのです。また、それができない自分を責めるようなこともやめましょう。
次に大切なことは、周りの人とのコミュニケーション。不安な気持ち、絶望的な感情を吐露できればいいのですが、立場や状況によってはそうもいきません。皆が気を張っている今、本当の気持ちを吐き出すには実は相当時間がかかります。あいさつでもいい、そっと触れるだけでもいい。とにかく、人の温かさを感じることが気持ちの安らぎにつながります。
家族や友人が被災地にいる、または安否が確認できないなどの状況に置かれている人も少なくないでしょう。気をつけるべきことは自分自身の気持ちが不安定な状態で無理に誰かを救おうとしないこと。自身が安全を確保していることに罪悪感を抱く必要もありません。引き続き災害に備えながらも、可能な限りの日常生活を続けることが心のペースメーカーとなります。
不安に駆られるときは、自分の気持ちや心配事をできる限り言葉にしたりリストアップしたりすると落ち着きます。
自分自身を冷静に見つめる
怖れは次の怖れを喚起します。自分自身の「怖さ」という気持ちのフィルターがかかった情報は、不安や焦りばかりが先行して伝播してしまいます。無用なパニックを避けるためにも、まず自分自身の気持ちをスクリーニング(ふるい分け)してみてください。
たとえ、被災地から遠いところにいる方でも、映像などで十分にショックを受けている可能性があります。自分自身が疲れや無力感を感じていること、不安や怖れを感じていることを踏まえた上で冷静な言動を心がけて下さい。そして自分自身の安全と健康確保も忘れずに。
休むことや食べることに罪悪感を持つことはありません。あなたが健康でいることも立派な支援です。無計画で衝動的な援助欲求は状況の混乱を招くだけでなく、燃え尽きなどによる共倒れの危険性をともなうことがありますので注意が必要です。
専門家のケアも大切
すでに大震災に関する報道の合間に、「テレビを観ている人もPTSDになる可能性があります」などというコメントを目にして不安を感じた方もいらっしゃるかもしれません。
確かにPTSDは誰もがなる可能性はありますが、大きな災害や事故に遭った方すべてがなるわけではありません。以下に、医療現場で用いられている診断基準の概要を紹介します。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
PTSD(心的外傷後ストレス障害)
危うく死または重傷を負うような出来事を体験、または本人や他者の身体の保全に迫る危険を体験・目撃・直面した。加えて、本人が強い恐怖や戦慄、無力感を覚えた。子どもの場合は極度の興奮として現われる場合も。このような体験をし、以下の基本症状が1ヵ月以上にわたって見られる場合にPTSDと診断される。
【PTSDと診断するための基本的症状】
・心的外傷と関連した出来事の追体験(フラッシュバック、悪夢など)
・心的外傷と関連した出来事に関連するものへの回避傾向、記憶障害、孤立、感情鈍麻、意欲減退など
・睡眠障害、易怒傾向、過度の警戒心や驚愕反応など
(参考文献:DSM-IV 該当項目の要約)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
大震災の爪痕が残る地で緊張を強いられながら過ごした後、上記のような症状が1ヵ月以上続く場合は専門家の診断の上で適切なケアをすることが求められます。実際にPTSDかどうかの判断や薬の処方は医師でないとできませんので、思い当たることがあれば医療機関や専門機関でのケアをおすすめします。
本人には自覚症状がなくても近親者がいつもと違う変化に気付くことでPTSDの兆候を早期発見できる場合もあります。
まだまだ新たな地震が続いており、心休まる暇もない方がたくさんいらっしゃることと思います。非常時に適応しようとする自分の心の力を信頼しながら、大切な方々と声を掛け合ってこの難局を乗り切っていきましょう。
【参考文献】
『DSM-IV』アメリカ精神医学協会
『心的外傷の危機介入』金剛出版
『グリーフワーク』アスク・ヒューマンケア
三吉野 愛子=心理カウンセラー
Posted by ほこぴー at 11:46│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。